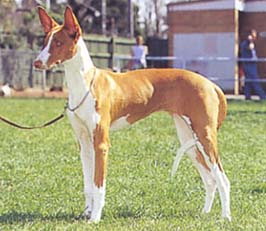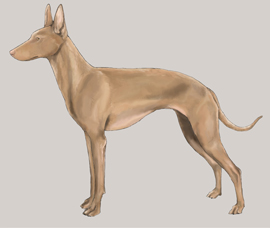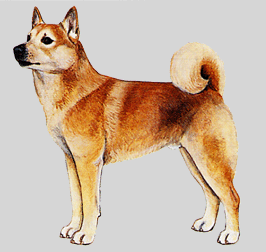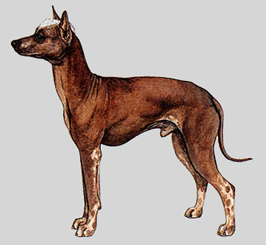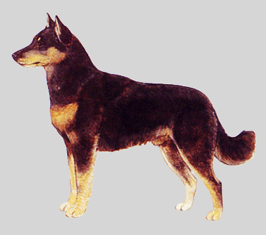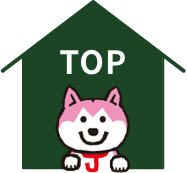秋田
- AKITA

スタンダードNo:255
原産地:日本
用途 :家庭犬
沿革 :古来秋田地方には秋田マタギ犬(熊猟犬)がおり、1868年以降は秋田マタギと土佐やマスティフとの交雑が行われ、より大型化したがスピッツタイプの特徴は失われた。
1919年に天然記念物保存法が発令され、保存運動がおこり、秋田は大型日本犬として改良保存が図られ、その結果、1931年に9頭の優秀犬が天然記念物として指定を受けた。 しかし第2次世界大戦(1939-1945年)中は軍用の防寒衣料として犬の毛皮を使用することとなり軍用犬のジャーマン・シェパード・ドッグ以外の犬には捕獲命令が出されたので、その捕獲を逃れる目的で秋田にジャーマン・シェパード・ドッグを交配した為、益々、交雑が進んでしまった。
終戦(1945年)後の秋田の状況は、数は激減し、タイプも混迷を呈していた。心ある犬識者たちはマタギ秋田タイプの犬たちを繁殖に使って外来犬の特質を 除去することに努め、今日の大型犬種として固定化した。

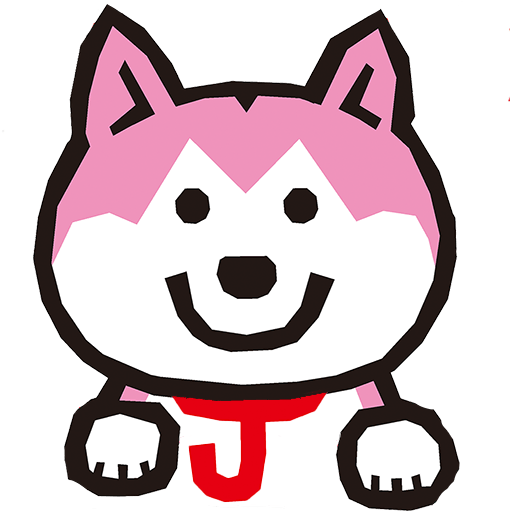
 検索
検索 ダウンロード
ダウンロード FAQ
FAQ